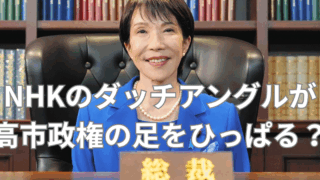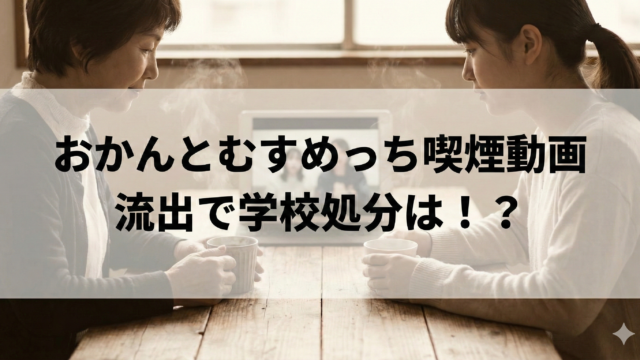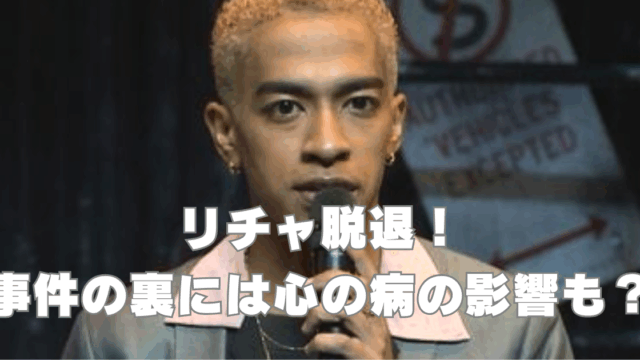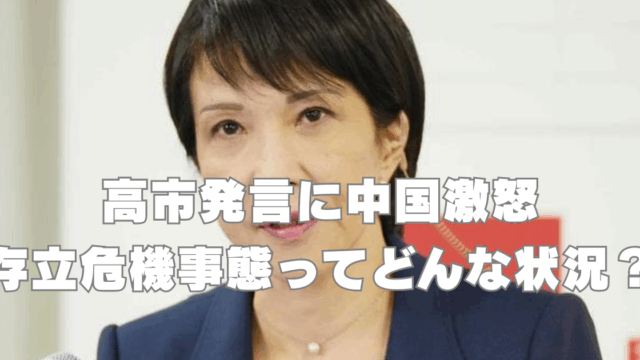大阪万博のネガティブキャンペーン報道がひどかった話
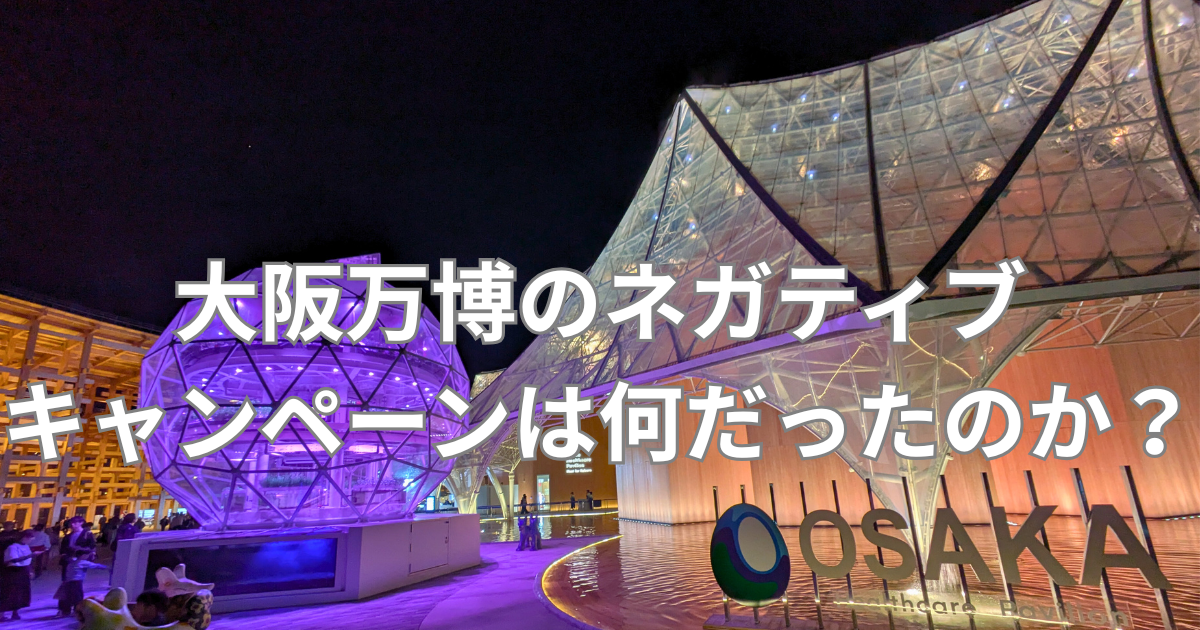
大成功に終わった2025年の大阪・関西万博。
皆さんは、覚えていまでしょうか?
開幕前に流れていた「失敗確定」「ガラガラ必至」といったネガティブ報道の数々を。
今考えると、マスコミのあのネガティブキャンペーンは何だったんですかね。
蓋を開いてみれば、聴こえてきたのは人々の感動が勝ったリアルな声でした。
テレビや記事よりも、現地の投稿や動画が信頼を集め、体験発信がニュースを凌駕する瞬間を、私たちは目撃していたのです。
そして、大阪万博が残した最大のレガシー。
それは、批判を乗り越えるほどの熱狂を生んだ人々の記憶ではないでしょうか。
今回は大阪万博を体験して見えてきた、マスコミのネガティブキャンペーンがなぜ生まれ、そこから学べたことについてわかりやすくまとめていきたいと思います。
大阪万博のネガティブキャンペーンとは

思い出してみてください。
まだ大阪・関西万博が始まる前、テレビをつければ「工事が遅れてる!」「地盤が沈むかも!」「メタンガスが危ない!」と、まるで災害速報みたいなニュースが毎日のように流れていました。
ネットやSNSでも「ガラガラ確定」「維新の無駄遣い」といった書き込みが広がり、反維新の空気が濃くなっていました。
「どうせ失敗する」「大阪のイベントは派手なだけ」――そんな言葉があちこちで聞こえたのを、覚えている人も多いはずです。
でも、ふたを開けてみれば結果は真逆。
会場は毎日が人・人・人!
連日20万人を超える来場者で、最終的には2557万人を突破。
過去の愛・地球博を上回り、国内歴代2位の大成功となりました。
一部のメディアは、建設費の増加や一部パビリオンの遅れを大きく取り上げ、「失敗確定」と断定的に報じていました。
でも実際は、世界158か国が参加し、空飛ぶクルマやiPS技術、未来のエネルギー展示など、内容はまさに未来の見本市。

現場では笑顔と感動があふれていました。
なぜ、そんなにネガティブな報道が多かったのか。
背景には、政治的な対立と商業的な話題づくりの両方があります。
大阪維新の会が強く推進し、国や経済界と連携したプロジェクトだったことから、「維新の手柄」と見られがちでした。
そこに一部メディアが「失敗ありき」で報じる構図が生まれ、視聴率を狙ったセンセーショナルな見出しが増えたのです。
もちろん、問題を指摘するのは大切です。
でも当時のトーンは監視というより断罪に近いというか、「また大阪がやらかすぞ」という冷たい雰囲気が漂っていました。
その結果、「やっぱり大阪はダメだ」という先入観を持つ人も多く、私もすっかりそんな印象に飲み込まれてしまってました。
けれど実際に行ってみたら、そんなネガティブな報道とはまるで別世界。
スタッフやボランティア、家族連れが「万博おもしろいよ!」と盛り上がり、SNSでも「あれがいい!」「ここが最高!」という投稿が一気に広がっていきました。
『#大阪万博』が何度もトレンド入りし、「ミャクミャク可愛い!」「未来を感じた!」とポジティブな声が殺到。
(たしかに。めちゃめちゃミライを感じた!)

まさに池井戸潤のドラマにあるような逆転劇がリアルタイムで進行していたのです。

ミャクミャクのグッズは完売が続き、空飛ぶクルマには「乗りたい!」という声が殺到。
能登の輪島塗展示には300万人が足を運び、被災地への応援メッセージがあふれました。
こうした感動体験がSNSで拡散し、“失敗確定ムード”を見事にひっくり返したのです。
なぜ大阪万博は成功できたのか?
 夕陽がきれいだったなぁ…
夕陽がきれいだったなぁ…
あれだけ「ガラガラ確定」「失敗する」と言われていたのに、ふたを開けてみれば来場者数は右肩上がり。
後半は連日20万人を超える人出となり、ピーク時には22万人以上が訪れ、最終的には2557万人の来場者を記録。
世界規模の博覧会の来場者数としては、国内歴代2位という大記録を打ち立てたのです。
では、なぜこんな奇跡のような逆転が起きたのか。
答えは“現場の力”にあったように感じました。
まず、すべてを支えたのはスタッフやボランティア、そして来場者たちの一体感。
会場内では明るいオーラが漂い、みんなで声を掛け合いながら楽しそうな雰囲気に包まれています。
(後半20万人を超えた辺りから、そういう空気感も減ってきましたが…苦笑)
たとえば、インドネシアパビリオンでの「ヨヤクナシデスグハイレル」という曲だったり、警備員さんのジョークを交えた誘導だったり、その明るさと前向きさが、どんな批判も吹き飛ばしていったのです。
そしてもう一つの特徴が、SNSでの情報共有がすごかったこと。
SNSでは様々なお得情報が飛び交いました。
- 3日前予約の攻略方法
- パビリオンの見どころ
- 会場の周り方
- 美味しいレストランやカフェ
- 当日予約を取る方法
- タクシーのシェアライド
などなど。
大阪万博の花火、火力レベチすぎて盛大にぶっ飛ばした pic.twitter.com/drM4U8T0Hu
— けいしろ/星配り (@keishirooooon) October 13, 2025
現場とSNSが見事につながって、まるで全国が一緒に“参加してる気分”になったんです。
さらには夜の大屋根リングの光景や、世界のグルメを楽しむ家族の笑顔。
投稿はどれもリアルな体験の共有でした。
わしのFFさんに関西民おりゅ?🙄
…万博ロスになってない?
俺はなってるで🥲
大阪市役所前にミャクミャク様がまだいるんで載せときますね! pic.twitter.com/StCV8H83ul— 大阪雷音 (@DJ_Osaka_Raion) October 21, 2025
そして閉幕後も「#大阪万博」は話題が続き、「ミャクミャクのグッズ、完売した!」「また行きたい!」という声が止まりません。
2557万人の感動が、SNSを通してまだ広がり続けているのです。
もちろん、経済的にも成果は大きく、大阪・関西を中心に、全国で約2.9兆円の経済波及効果が期待され、飲食や観光、宿泊など、さまざまな業界が潤いました。
私が利用したタクシーの運転手さんも「万博のおかげで忙しい」と言ってましたし、ホテルの料金も駐車場の料金も万博開催期間中はどこも高需要でした。
閉幕後も、熱は冷めません。
大屋根リングの一部保存や博物館構想が動き出しているようで、「この場所をどうレガシーとして残すか」が次のテーマになっています。
なんにせよ、2025年の大阪万博を体験できたことは、この先何十年にも渡って話のネタになるし、逆風を吹き飛ばしての万博大成功というのは日本にとっても良い影響になるのは間違いなさそうです。
メディアコントロールを無効化し、利用者全体の温かさとポジティブさでつかんだ成功と言えるでしょう。
それが、今回の万博のいちばんのレガシーなのかもしれませんね。
大阪万博のネガティブ報道が残した教訓

あれだけ「失敗する」「税金のムダだ」と言われていた大阪・関西万博。
でも、フタを開けたら会場は笑顔であふれ、関西を中心に日本中を盛り上げました。
ネガティブな報道の嵐をくぐり抜けての大成功。
そこには、私たちが学ぶべき大きな教訓があります。
まずひとつ目は、「ネガティブな空気がどれだけ現実をゆがめるか」。
これはすごく重要なことだと思います。
開幕前のニュースを思い出してください。
テレビでは「工事が遅れている」「海外パビリオンが間に合わない」と連日報じられ、ネットでは「維新の失敗」「ガラガラ確定」「税金の無駄」といった投稿が飛び交っていました。
たしかに、課題はありました。
でも、その一方でポジティブなパワーで大阪の経済を活性化させた現場の熱を大事にすることは、何よりも我々が学ぶべきことなのかもしれません。
そして、もう一つの教訓が「発信の力の主役が変わった」ということ。
かつてはテレビや新聞が事実を決めていました。
でも今は違います。
SNSで投稿された一枚の写真や一言の感想が、空気を変える時代です。
「#大阪万博」「#ミャクミャク」などのハッシュタグが何度もトレンド入りし、大阪万博への注目度が徐々に全国に広がっていきました。
閉幕後も「#大阪万博」がトレンド入りし、「ミャクミャク最高!」「また行きたい!」と投稿が続出。
つまり、情報の主役は報道から体験へと移った。
大阪万博が教えてくれたのは、「誰が言うか」ではなく、「ミャクミャクの可愛さ」や「未来の技術のワクワク」をどう感じたかが大事だということです。
さらに今、夢洲では次のステージが動き始めています。
 大屋根リングからの眺めきれい!
大屋根リングからの眺めきれい!
政府のレガシー会議では、大屋根リングの一部保存や未来の公園化、そして黒字230〜280億円を奨学金や地域整備、博物館整備などに活用する案が検討されているとのこと。
ミャクミャクのグッズは売れに売れ、空飛ぶクルマは「2028年に乗れる!」と話題になり、能登の輪島塗展示には300万人が訪れて被災地を応援しました。
万博の感動は、今も未来へとつながっています。
そして今、市民のアイデアで「どんな夢洲にしたい?」という議論が始まっています。
このパワーこそが万博の最大のレガシーであり、これはもう行政や企業だけのものではありません。
そこでポジティブな体験をした人たちが、次の時代をつくっていく気がするのです。
いま振り返っても、大阪万博に対するネガティブキャンペーン報道は何だったんだろうと思います。
大阪万博が成功したからいいものの、あの足を引っ張る報道姿勢って本当に良くないですよね。
だって、事実と違うことを大きく報道していたのですから。
でも、その逆風があったからこそ、私たちは気づいたのです。
「情報に流される時代から、自分で感じる時代へ」
前を向いて、ポジティブな未来を信じる。
それが、大阪万博が残した一番のレガシーであり、ネガティブキャンペーン報道を超えた希望の物語だったのかもしれませんね。